博士課程学生 蜂須賀氏の挑戦と、プログレッシブ・フォトン・マッピング
実用化とのつながりがクリアな、アメリカのCG研究
Jensen氏の研究と、産業界との新たな融和

(C) National Graphics, Image Courtesy : Henrik Wann Jensen
前編で紹介したように、Jensen氏が考案したサブサーフェース・スキャタリング・モデルは、 サブサーフェース・スキャタリングという現象が作り出すビジュアル的な効果を、CGという分野を超えて広く世に知らしめることになった。上の画像は、米国誌National Graphicsとの共同プロジェクトで作成されたもので、同誌の2002年11月号の表紙を飾った。
Jensen氏が考案したサブサーフェース・スキャタリング・モデル(Subsurface Scattering)では、本来物理的には非常に複雑なマルチプル・スキャタリングの効果を、1組の仮想的な点光源(ダイポール:Dipole)という、CGアーティストにとって非常にわかりやすいモデルで近似することができる。このような利点は、とりわけ映画のVFXやフル3DCG映画などの制作現場に大きなインパクトを与え、論文発表から1年とたたないうちに、様々な映画プロジェクトで用いられるようになった。Jensen氏自身がこのような映画プロジェクトに関わる機会も増え、苦い経験を味わったmental images社での市販ツール開発とは違った形で、理論的な研究とそれを応用する産業界との交流に貢献してゆくことになった。そして時を同じくして、Jensen氏はカリフォルニア大学 サンディエゴ校(UCSD:University of California, San Diego)のAssociate Professorに就任した。
就任直後のJensen氏は、自身の研究室をどのように盛り上げていこうかと色々思案していたようだ。教える立場への突然の転向だったため、ある種の気負いのようなものがあったのかもしれない。結果としてJensen氏のもとには、これまで同氏が考案してきた手法をさらに進化させることを目指す学生が自然と集まるようになった。ダイポール・モデルをマルチレイヤーに対応できるように改善するなど、人間の皮膚の表現において非常に画期的な業績を残したCraig Donner氏はその代表例といえるだろう。



マルチレイヤー対応のサブサーフェース・スキャタリング・モデル
Image Courtesy : Craig Donner
Jensen氏が考案したダイポール・モデルは、1つの層内でのマルチプル・スキャタリングしか表現できなかった。Craig Donner氏は、マルチポール(Multipole)という概念を導入し、幾重にも重なった層内(マルチレイヤー)でのマルチプル・スキャタリングを物理的に正確に表現することを可能にした。この手法はSIGGRAPH 2003で発表され、大きな話題となった。左の画像は、マルチレイヤー対応のサブサーフェース・スキャタリング・モデルを用いて、表層(Epidermise)と深層(Dermise)の2層からなる人間の皮膚をレンダリングした結果を示している。口周りのクローズアップ画像2点は、マルチレイヤー・モデルを用いてレンダリングした結果(中央の画像)と、ダイポール・モデルを用いてレンダリングした結果(右の画像)を比較したものである。
そして同様に、現在フォトンマッピング法(Photon Mapping)の改善において画期的な研究成果を生み出しつつあるのが、日本から博士課程の学生としてJensen氏の研究室に加わった蜂須賀 恵也(はちすか としや)氏だ。前編で紹介したように、フォトンマッピング法はコースティクス(集光模様)の生成のみならず、グローバル・イルミネーション(GI:Global Illumination)の計算にも活用できるのだが、後者の面ではまだまだ多くの改善点が見込まれている。蜂須賀氏が目指しているのは、主にこのグローバル・イルミネーションにおけるフォトンマッピング法の改善である。横浜で開催されたSIGGRAPH Asia 2009で蜂須賀氏が発表し、着実に改善を進めているプログレッシブ・フォトン・マッピング(PPM:Progressive Photon Mapping)は、まさにその実現に王手をかけた手法といえる。Jensen氏はこの手法を高く評価しており、蜂須賀氏にことのほか期待している。
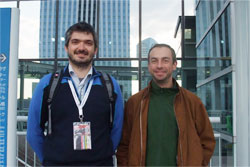
Weta Digital社との交流
Jensen氏の研究室は、2009年頃からWeta Digital社と交流を深めており、同社の映画プロジェクトを積極的にバックアップしている。上の写真は、SIGGRAPH Asia 2009における講演のために来日したWeta Digital社のLuca Fascione氏(Senior Software Developer)とのツーショット。
研究室全体の業績が安定してくるにつれて、教えることに対するJensen氏の気負いも薄れてきたようだ。現在は、自分自身と研究室全体とが、なるべく多くの目標を共有できるよう配慮した運営を、自然体で行っているように見受けられる。たとえばJensen氏は、「AVATAR」の制作で知られるWeta Digital社の映画プロジェクトを2009年頃から積極的にバックアップしはじめており、自身も頻繁に同社を訪れている。そういった背景があってか、前述したDonner氏や蜂須賀氏は、一定期間インターンシップとしてWeta Digital社で学ぶ機会を得ている。この貴重な体験を通して、理論と、それを実用化する産業界との接点のあり方を考えていって欲しいというJensen氏の願いが込められているようだ。

カリフォルニア大学
サンディエゴ校
(アメリカ カリフォルニア州)
准教授(Associate Professor)
デンマーク出身。フォトリアリスティックレンダリングの分野を代表する研究者の1人。デンマーク工科大学(DTU)でCGを学び、1996年に博士号を取得。博士論文で発表したフォトンマッピング法は、同氏の代表的な研究成果の1つであると同時に、グローバル・イルミネーションの新理論として一世を風靡する。卒業後2年間mental images社に所属したのち、アメリカに渡り、1998年から1年間Postdoctoral ResearcherとしてMIT(マサチューセッツ工科大学)に在籍、1999年から2002年までスタンフォード大学のPat Hanrahan氏の研究室で学ぶ。 2001年に発表した画期的なサブサーフェース・スキャタリング・モデルは、フォトンマッピング法と並ぶ同氏の代表的な研究成果。このシンプルで効率的なサブサーフェース・スキャタリング・モデルは、数々の映画プロジェクトで活用されるようになり、その功績によりScientific and Engineering Academy Awardを2004年に受賞する。また2001年にはグローバル・イルミネーションの名著『Realistic Image Synthesis Using Photon Mapping』をAK Peters社から刊行、翌年には苗村健氏による翻訳版『フォトンマッピング- 実写に迫るコンピュータグラフィックス』もオーム社から刊行された。 2002年にカリフォルニア大学 サンディエゴ校(UCSD)の准教授(Associate Professor)に就任、2003年からは高速なライトシミュレーション技術のサポートを目的にLuxion社のアドバイザーも兼任するようになり、現在に至っている。同氏のサポートのもとでLuxion社が開発したKeyShotというリアルタイム・グローバルイルミネーション・ツールの最新バージョンは日本語版でのリリースも予定されている。 研究や教育活動の詳細はこちらで紹介されている。
