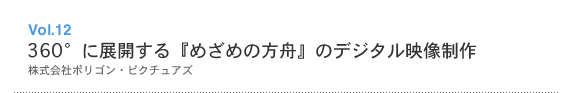愛知万博の7社共同パビリオン「夢みる山」で上映された、押井守監督の総合演出によるテーマシアター『めざめの方舟』が大きな話題を呼んだ。押井監督は、カンヌ国際映画祭に日本のアニメ史上初めてノミネートされた映画『イノセンス』でおなじみのジャパニメーションの巨匠。シアターは円筒形で、床には50インチのプラズマディスプレイ96台を敷き詰めた「床面プラズママルチディスプレイシステム」、その周りには動物のキャラクターを立像化した139体の巨大擬人像「六将」が3~4列に立ち並び、天井には世界初の長径5m・タマゴ型(3次元)アクリルスクリーンをはじめとする大小8基のスクリーンが取り付けられ、太古の森をイメージした巨大な美術造形が覆っている。
愛知万博の7社共同パビリオン「夢みる山」で上映された、押井守監督の総合演出によるテーマシアター『めざめの方舟』が大きな話題を呼んだ。押井監督は、カンヌ国際映画祭に日本のアニメ史上初めてノミネートされた映画『イノセンス』でおなじみのジャパニメーションの巨匠。シアターは円筒形で、床には50インチのプラズマディスプレイ96台を敷き詰めた「床面プラズママルチディスプレイシステム」、その周りには動物のキャラクターを立像化した139体の巨大擬人像「六将」が3~4列に立ち並び、天井には世界初の長径5m・タマゴ型(3次元)アクリルスクリーンをはじめとする大小8基のスクリーンが取り付けられ、太古の森をイメージした巨大な美術造形が覆っている。そして、床面あるいはスロープに立った観客は、360°の実写とCGの合成デジタル映像、それも天井を見ても、床面を見ても、壁面を見ても全部が違う映像と照明、音響の奔流に全身が覆い尽される。その日常感覚を超えた圧倒的な迫力に、シアターは会期中引きも切らぬ人気となった。
人間が壊しかけている地球環境を取り戻すため、地球上で共に生きている自然と動物たちに目を向かわせようという『めざめの方舟』は、「海-水の記憶-靑鰉(SHO-HOW)」、「空-時を渡る-百禽(HYA-KIN)」、「大地-未生の記憶-狗奴(KU-NU)」の3本のプログラムをそれぞれ2ヶ月ごとに更新していった。プログラムに合わせて映像を変えるとともに、巨大擬人像の頭部も「魚の頭を持つ靑鰉」、「鳥の頭を持つ百禽」、「犬の頭を持つ狗奴」と変わっていった。
 映像演出担当の林弘幸氏との連携のもと、この360°の体験型映像空間をフルに活用した驚異的な映像を制作したのが、ポリゴン・ピクチュアズだ。
映像演出担当の林弘幸氏との連携のもと、この360°の体験型映像空間をフルに活用した驚異的な映像を制作したのが、ポリゴン・ピクチュアズだ。テクニカルディレクターとしてデジタル映像制作の全体統括と最終的な仕上げを行ったCGIアーティストの生田芳仁氏は「実質的な制作期間は半年間。しかも各約10分の360°をカバーする映像を3プログラム分完成させなければなりません。制作ボリュームが多く、時間が少なかったため、モデラー、アニメーター、キャラクターセットアップ、コンポジット&レンダリングの
 20人の制作スタッフで、プライオリティの高いところ、できそうなところからどんどん着手していきました。当初のテストを兼ねたデモCGで、押井監督のコンセプトや林さんのイメージが完成形に近く、ビジョンがしっかりとしていたため、制作はやりやすかったです。後は時間との闘いでした」と語られる。
20人の制作スタッフで、プライオリティの高いところ、できそうなところからどんどん着手していきました。当初のテストを兼ねたデモCGで、押井監督のコンセプトや林さんのイメージが完成形に近く、ビジョンがしっかりとしていたため、制作はやりやすかったです。後は時間との闘いでした」と語られる。その映像表現は、たとえば「海-靑鰉」では、海に暮らす生き物たちの姿が全面に映し出され、雷鳴をきっかけに映像が変化 。 天井のタマゴ型アクリルスクリーンから魚や亀の目がぎょろりと覗いたりする。大海原を舞台に、森羅万象の転変や過去から現在、未来へと環境の変遷がダイナミックに描かれていく。最後に森羅万象の象徴である、3つの顔と6つの手を持つ精霊"汎"が天井から下がり全貌を現す。
「『海』は最初につくったので、まだ時間的な余裕があり、3本の中でも一番数が多い10数種のキャラクターをつくりました。シーラカンスもいます。靑鰉と百禽は架空の生物なのでイメージをつかむのが難しく、デザイン自体を何度もやり直しています。狗奴は押井監督の思い入れが強いキャラクターでした。サルーキーという犬種が指定されていましたので、モデリング担当スタッフが犬のいる場所に取材に行き、細部まで観察して監督の注文どおりの見た目や表情や動きを再現しました」と生田氏。
 キャラクターづくりとともに、制作でとくに苦心したのは、『海』と『空』の場合では、雲の表現だったという。「"実写でもいいけど、やはりクオリティの高いCGで表現したい"と林さんがおっしゃったのでチャレンジしました。台風の目を上から見たときの渦巻く雲のレンダリングでは1枚作成するのに3~4時間。それを何百枚もつくるために、レンダリングファーム50台をフルに駆使しても2ヶ月かかりました」
。
キャラクターづくりとともに、制作でとくに苦心したのは、『海』と『空』の場合では、雲の表現だったという。「"実写でもいいけど、やはりクオリティの高いCGで表現したい"と林さんがおっしゃったのでチャレンジしました。台風の目を上から見たときの渦巻く雲のレンダリングでは1枚作成するのに3~4時間。それを何百枚もつくるために、レンダリングファーム50台をフルに駆使しても2ヶ月かかりました」
。 さらに、百禽の羽毛や狗奴の銀髪など「ファー」の表現や動きは物量が多いうえに、レンダリングサーバに分散させるとチラチラしてしまうため、ドローイングしてからCG化したり、手付けアニメーションとシミュレーションの良いとこ取りをする工夫をしたという。
生田氏は「言葉でできないものを映像で表現したいというのが押井監督です。こちらが迷うとダメですから、監督や林さんが思うことをさらに昇華させたものを提案し、制作してきました」と語られ、映像の世界観をスタッフと共有するために、プロジェクトごとに朝会を開き、作業計画とスタッフが興味のあることを聞きだしながら、作成物のチェック&アドバイスを繰り返してきたという。
こうして最終的に仕上げられた映像を放映するため、会場での映像システムをつくり上げていったのが、CGIエンジニアの亀田慶一氏だ。
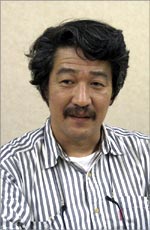 亀田氏は「画像を床面96台のディスプレイと天井の3台のタマゴ型スクリーンに分けるために、自動的に生田さん達がつくった画像を99台のハードディスクプレイヤー用のムービーファイルに変換するプログラムと、出来たムービーを実際のハードディスクプレイヤーへ転送するプログラムをつくりました。壁面は別のシステムにして、手作業で3パターンつくっています」と、システムプログラムの構成を紹介。
亀田氏は「画像を床面96台のディスプレイと天井の3台のタマゴ型スクリーンに分けるために、自動的に生田さん達がつくった画像を99台のハードディスクプレイヤー用のムービーファイルに変換するプログラムと、出来たムービーを実際のハードディスクプレイヤーへ転送するプログラムをつくりました。壁面は別のシステムにして、手作業で3パターンつくっています」と、システムプログラムの構成を紹介。とくに、床面のプラズママルチディスプレイシステムは、世界で初めて高精細画像を縦約9メートル、横約10メートルの大画面に1枚絵として映し出せるため、解像度がとても気になったという。「こんなに大きい画面は初めての経験でした。自分が理想とする解像度には到達できませんでしたが、99台のディスプレイで高解像度の映像を表現できたという達成感と自信はあります。つくば博や花博も手がけたことがありますが、今回はデータ量が生半可ではありません。それを期限内にシステム面で可能にできたのは、とても満足です」と亀田氏。
生田氏は「完成後、制作スタッフ全員で会場へ見に行きましたが、やはり360°の映像と音楽が織り成す迫力にはとても感動しました。今後も、時間とスタッフの人数という制約の中でもベストを尽くした仕事をやりたいですね」と抱負を語る。
 |
 |
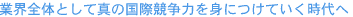
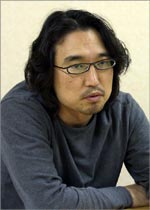 ポリゴン・ピクチュアズはCG制作の先駆であり、実績、規模ともに日本でトップクラスのCGクリエイター集団。3DCGを駆使した映画やテレビ番組、CM、ゲーム、R&Dなどを幅広く手がけ、『ポリゴン家族』や『デジタル所さん』などのキャラクターづくりでも知られる。その輝かしい受賞暦は国際アニメーションフェスティバルやSIGGRAPH、ARS
ELECTRONICA、ACC CMフェスティバルなど数限りない。
ポリゴン・ピクチュアズはCG制作の先駆であり、実績、規模ともに日本でトップクラスのCGクリエイター集団。3DCGを駆使した映画やテレビ番組、CM、ゲーム、R&Dなどを幅広く手がけ、『ポリゴン家族』や『デジタル所さん』などのキャラクターづくりでも知られる。その輝かしい受賞暦は国際アニメーションフェスティバルやSIGGRAPH、ARS
ELECTRONICA、ACC CMフェスティバルなど数限りない。
数々の賞の審査員を務め、かつ自民党の小委員会で「デジタルコンテンツ産業の課題」というテーマで講演した経験もある塩田周三社長は、「日本のクリエイターは本当に優秀ですが、CGアニメーションなどは米国と比べ予算面でケアされていないのが実情です。デジタルコンテンツ業界全体として、これからは北米や中国、インドなどの海外と闘う力が必要です。そのためには、組織力を活かして制作の効率化を図る"インダストリー"というやり方や、いま日本で欠如しているビジネスセンスと国際性を高めることが重要になります」と、今後の業界のあるべき姿を語られる。
![]()
これからの若い人材に期待するものとして、塩田社長は「若い方は、1人のクリエイターに対し、各専門パートを担う100人のワーカーが必要である、というデジタルコンテンツ業界の現実を直視してください。夢と情熱、才能を持った人しか、生き残れません。そして、クリエイター志願にしろワーカー志願にしろ、自分が何をやりたいか、自分がどこのパートを担うのが最適かを見極めてください。それがプロへの道です」と、自己を持ち上げる力、自分を見極める目が必要だという貴重なアドバイス。
 また、生田氏は「CGは勉強すればできるようになります。大切なのは発想力とイマジネーションです。自分のクオリティを高めるために、映画や演劇、コンサートなど何でもいろいろなものを見聞きしてください。また、時間に対する意識やチームワークなどのバランス感覚が必要です」とエールを送られる。さらに、亀田氏は「何を見ても、まずは面白いと思う気持ち。たとえば、葉っぱが落ちるのを見たら、その動きを表現するには、どうプログラミングすればいいかを考えてみてください」とプログラミングとアートの両方を実践してきた方ならではの言葉が光った。
また、生田氏は「CGは勉強すればできるようになります。大切なのは発想力とイマジネーションです。自分のクオリティを高めるために、映画や演劇、コンサートなど何でもいろいろなものを見聞きしてください。また、時間に対する意識やチームワークなどのバランス感覚が必要です」とエールを送られる。さらに、亀田氏は「何を見ても、まずは面白いと思う気持ち。たとえば、葉っぱが落ちるのを見たら、その動きを表現するには、どうプログラミングすればいいかを考えてみてください」とプログラミングとアートの両方を実践してきた方ならではの言葉が光った。