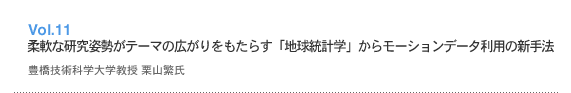栗山繁氏は現在、豊橋技術科学大学教授として、ヒューマノイドアニメーション、Web3D、ユビキタス画像情報と幅広い分野で研究活動を展開している。大学時代、大阪大学の大村皓一助教授の研究室でCG用並列プロセッサー、「LINKS-2」の開発に携わったのち、人工知能、自由曲面(特に、媒介変数曲面)の研究などを行い、曲面の研究で修士を卒業後、論文博士号も取得、IBM東京基礎研究所でも曲面の研究を続けてきた栗山氏。「当時からCGを研究しているという意識はそれほどなくて、自由曲面の研究をやっているときにもやはり、応用数学の研究と考えていました」と話す。「その後、広島市立大学に転職後、情報系の学生に興味を持ってもらえるCG寄りの研究テーマが良いかと思い、自由曲面からポリゴン曲面に鞍替えしましたけど」。豊橋技術科学大学では「ゲーム会社の人と話した機会があったのですが、それがきっかけとなってアニメーションをやり始めました」と言う。栗山氏自身「あまり自分の研究に対するポリシーはないかもしれない」と自嘲気味に話すが、その研究成果の過程を拝見すると、枠にとらわれず、新しい研究対象に対する柔軟な姿勢が、学問の中で新たな発見をもたらすことを、身をもって証明しているかのように見えるのだ。
栗山繁氏は現在、豊橋技術科学大学教授として、ヒューマノイドアニメーション、Web3D、ユビキタス画像情報と幅広い分野で研究活動を展開している。大学時代、大阪大学の大村皓一助教授の研究室でCG用並列プロセッサー、「LINKS-2」の開発に携わったのち、人工知能、自由曲面(特に、媒介変数曲面)の研究などを行い、曲面の研究で修士を卒業後、論文博士号も取得、IBM東京基礎研究所でも曲面の研究を続けてきた栗山氏。「当時からCGを研究しているという意識はそれほどなくて、自由曲面の研究をやっているときにもやはり、応用数学の研究と考えていました」と話す。「その後、広島市立大学に転職後、情報系の学生に興味を持ってもらえるCG寄りの研究テーマが良いかと思い、自由曲面からポリゴン曲面に鞍替えしましたけど」。豊橋技術科学大学では「ゲーム会社の人と話した機会があったのですが、それがきっかけとなってアニメーションをやり始めました」と言う。栗山氏自身「あまり自分の研究に対するポリシーはないかもしれない」と自嘲気味に話すが、その研究成果の過程を拝見すると、枠にとらわれず、新しい研究対象に対する柔軟な姿勢が、学問の中で新たな発見をもたらすことを、身をもって証明しているかのように見えるのだ。最新の研究論文にもその、柔軟なアプローチが存分に生かされている。2005年8月のSIGGRAPHのペーパーで採択された、博士課程学生の向井智彦と栗山繁教授による論文「Geostatistical Motion Interpolation」(地球統計学的な動作の補間法)は、複数のモーションキャプチャデータを、的確な割合で組み合わせることにより理想の動きを効率的に作り出すための技術について書かれている。その、的確な割合で動きのデータを組み合わせる方法として用いられているのが「地球統計学的な動作の補間方法」である。
地球統計学とは、もともと、地中に埋もれている石油や鉱物、海中の魚群の探知など目に見えない資源を少ないデータから推測する技術だ。一種のデータマイニングの技術であり、天気予報などにも用いられる。この技術を、モーションキャプチャデータから的確なサンプルデータを選び出し、適切な割合で理想の動きとして合成するために用いている。モーションキャプチャデータの利用については、データの合成や編集などについてすでにさまざまな研究がなされているが、より、効率的、インタラクティブでしかも精度の高いものを作り出そうとしたのが、本研究といえる。
「すでに10年以上前から動作データを混ぜ合わせて新しい動作データを作り出す方法は研究されています。最終的に作り出したい動きのデータを正確に計算するには、複数の動きデータから、どのデータをどのぐらいの割合で取り出し、ブレンドするかを導き出さねばならない。しかしこれまでは、それぞれのデータの分布の状態を定量的に推定する方法がなかったために、正確な合成ができませんでした」(栗山氏)。
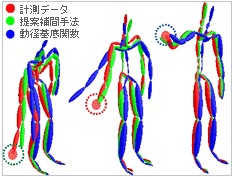 今回の手法では、「有限個の(動き)サンプルデータを用いて、任意のパラメータ空間全体の連続的なデータ分布を予測する」というように、時系列での各姿勢を、合成を操作するパラメータ空間の座標値としてとらえ、その座標値の「統計的空間分布予測問題」として扱っている。それによって、最終的な姿勢に対して、サンプルデータの組み合わせ割合を推定する基準を確立している。その統計的な推定方法によって、的確な動きを予測でき、さらに必要最小限のサンプルを選び出すことも可能になる。
今回の手法では、「有限個の(動き)サンプルデータを用いて、任意のパラメータ空間全体の連続的なデータ分布を予測する」というように、時系列での各姿勢を、合成を操作するパラメータ空間の座標値としてとらえ、その座標値の「統計的空間分布予測問題」として扱っている。それによって、最終的な姿勢に対して、サンプルデータの組み合わせ割合を推定する基準を確立している。その統計的な推定方法によって、的確な動きを予測でき、さらに必要最小限のサンプルを選び出すことも可能になる。具体的には「姿勢距離測度を用いて動作間の相関を効率的に解析し、指定されたパラメータを満たす最適な補間カーネルを時間フレームごとに計算する。そして、合成動作における幾何学的な拘束位置をパラメータ空間内の座標値として表現することで,その拘束条件を満足する動作をほぼ正確に予測できる」。
この「動作間の相関を効率的に解析」する方法として使用しているのが、地球統計学におけるクリギングという手法だ。これは、鉱山や石油埋蔵量を予測するときに、複数の地点で得られたサンプリングデータから、一定区間内の連続的なデータ分布を予測する空間統計手法だ。
 二つの空間座標間の距離と、データの類似度(非類似度、乖離度)の相関関係を記述する統計モデルを利用し、ただ一つの相関モデルをサンプルデータから推定する。それにより、任意の予測位置に対して、他のサンプルデータとの非類似度を推定し、各サンプルへの重みづけを最適化する。
二つの空間座標間の距離と、データの類似度(非類似度、乖離度)の相関関係を記述する統計モデルを利用し、ただ一つの相関モデルをサンプルデータから推定する。それにより、任意の予測位置に対して、他のサンプルデータとの非類似度を推定し、各サンプルへの重みづけを最適化する。天気予報にたとえると、東京の天気を予測するために、神奈川と千葉、新潟、北海道のデータがあった場合、それぞれを東京からの距離によって重みづけをすることで、正確な東京の天気を予測しようというものだ。その際に、日本では地域間の距離によって天気がどの程度変動するかの予測値が必要となるが、それを求めるのがクリギング手法である。
このとき、前提となる条件が、「本質的定常性」と呼ばれるものだ。これは、確率場と呼ばれる空間内において、複数の地点で事象xが起きる確率をとり、それぞれの地点間の確率の差を求め、その平均値がゼロになり、さらに、その分散値が地点間の距離のみで決まる関数(バリオグラムと呼ばれる)として表現できる場合をさす。こうした本質的定常性の下では、ある事象が急激に変化するということはなく、極端な変動がない状態だといえる。これによって、確率統計的計算で信頼性が出てくる。基本的に、この本質的定常性に当てはまる動きは、その姿勢や振る舞いが徐々に変化する動作になる。たとえば、「階段を上る」とか「歩く」といった動きは、段差や歩幅の変化に対して徐々に様態が変化していくので、本質的定常性を有する。
こうして得られた動きを、実際の真の値と比較した結果、相対的に近い値が導きだされているという結果が出た。
 栗山教授は、今回の論文の意義について次のように話す。「狙いは、世の中にたくさんあるモーションキャプチャのデータを、いろいろな場面で使いやすく、しかも効率的に利用したいということです。モーションデータは、文章や画像などの他のデータと比較してはるかに扱いにくいものです。また、たくさんそろえればそれでいいというわけでもありません。そもそもデータとしての一貫性に欠けている部分があるので、やはりそれなりのアプリケーションや技術が必要になります。たとえば他のデータと同様に、今後は動作データを検索するという作業が一般化すると予想しています。今年のSIGGRAPHでも動作データの検索に関する論文が初めて掲載されましたが、我々は2年前からこの問題に取り組み、昨年のコンピュータアニメーションのシンポジウム(Symposium
on Computer Animation 2004)では、自己組織化マップを用いた検索インタフェースの研究を発表しました。」
栗山教授は、今回の論文の意義について次のように話す。「狙いは、世の中にたくさんあるモーションキャプチャのデータを、いろいろな場面で使いやすく、しかも効率的に利用したいということです。モーションデータは、文章や画像などの他のデータと比較してはるかに扱いにくいものです。また、たくさんそろえればそれでいいというわけでもありません。そもそもデータとしての一貫性に欠けている部分があるので、やはりそれなりのアプリケーションや技術が必要になります。たとえば他のデータと同様に、今後は動作データを検索するという作業が一般化すると予想しています。今年のSIGGRAPHでも動作データの検索に関する論文が初めて掲載されましたが、我々は2年前からこの問題に取り組み、昨年のコンピュータアニメーションのシンポジウム(Symposium
on Computer Animation 2004)では、自己組織化マップを用いた検索インタフェースの研究を発表しました。」「パブリックなものとして広める必要があるし、今の方法で100%かというとそうでもないところもあります。意外と地道なところで、まだ解決しなければいけないところがあるのです。今回の方法も、動作データを足し合わせるという考え自体は昔からあり、既存の技術と見られていたものです。しかし、精度の高さという点ではまだ追求する余地があり、今回は精度を高めるという点にこだわったことで、新しい技術を考えることに結びつきました。ある意味で、そういったこだわりを持つことが、技術の進歩には重要なのではないかと思うのです。新規性のある技術だけではなく、ちょっと昔を振り返って見て、実は、本当はこういうところがまだ詰めが甘いんじゃないかというものがあれば、十分にSIGGRAPH級の研究になるものがまだあるんじゃないかと思います。」
そもそも、この技術が開発された端緒は、大手自動車会社からの委託研究プロジェクトだった。工場の組み立てラインを設計する際に、作業効率を高めるためには、まず人間の動きをシミュレーションして、それを念頭に工具や部品の配置とコンベヤの速度などを決定しなくてはならない。「しかしそのために、200人もの作業員の動きデータを正
 確にシミュレーションするのは想像以上に困難であることが判った。」最終的には、Web3D上で作業シミュレーションができるツールに仕上げている。今回の研究成果はシミュレーションの精度向上に大いに役立つものとなったが、今後も更なる改良と拡張が必要であると感じているようだ。
確にシミュレーションするのは想像以上に困難であることが判った。」最終的には、Web3D上で作業シミュレーションができるツールに仕上げている。今回の研究成果はシミュレーションの精度向上に大いに役立つものとなったが、今後も更なる改良と拡張が必要であると感じているようだ。「私自身の手応えとしては、そんなに複雑なものではない室内環境の設計など、人間の数と行動パターンがある程度限定されたものでしたら、今の技術で十分に使用に耐えると考えています」。
さらに、今回の研究成果の用途は広がりを見せつつある。計算速度を非常に短くすることができたために、インタラクティブな利用方法もある。CGアニメ制作の現場で、アニメータが、作りたいアニメーションのために、必要な部分ごとのデータを集めて合成するといったことも可能になるという。「これまでカートゥーンというと、単にデフォルメをすることと捉えられますが、アニメータは、モーションデータをリファレンスとしては、使いたいと思っている。だけど、モーションデータから、自分が使いたいところを拾っていく作業が難しい。モーションデータを使いやすいようにあらかじめ変換してあげて、そこから後はアニメータが自分で好きなように演出しやすいようにするためのしくみをこれから研究していこうと思っています」。栗山氏は、OLMデジタルの安生健一氏らとともに、モーションキャプチャデータをアニメ制作に使うための研究開発を進めている。
栗山氏は、上記の研究の今後の方向性の一つに「『不気味の谷』をテーマにした研究」があるとして、その狙いを次のように説明する。「モーションデータは、アニメータから見るとそんなにうれしいデータじゃないんですね。なぜかというと、あまりにもリアルすぎて使えない。特に、2次元的なアニメのキャラクターにリアルな動きを入れると、違和感を抱くことがあります。人間型のロボットの開発では、森政弘氏東工大名誉教授が発表した、いわゆる「不気味の谷」というものがあると言われています。本物にだんだん近づけていくと、あるところで不気味な感じになるというもので、アニメーションにもそれがあります。大学でこれをテーマに、人間が自然のものをどういった条件で受け付けなくなるのかという、認知についても研究していきたいと思います。リアリティと反リアリティの境界、その背後にある現象を数値で割り出せないかなと思っています。」
栗山氏は、今後のテーマとして、もう一つ「行動のシミュレーション」についての、研究を挙げた。
 「都市工学などで、災害時に公共の空間で人間がどういうふうに動き、流れていくのかをシミュレーションすることがあります。あらかじめ予測することによって、建築物や公共空間の設計の時点で災害時の人の動きがスムーズになるようにモニュメントなどの位置を決めることができます。しかし、都市工学の分野は人間を非常にマクロな視点で扱います。要するに人間を点と見なして、その点がどう動くかというものです。なので、実際に身体的な歩きやすさといったところは、無視している。一方、CGアニメーションは非常にミクロな視点で、歩き方がどうなるかということを見ていますが、マクロな視点は欠けています。たとえば、映画で登場するCGの群集は自然には見えますが、それが人間の本当の感覚や行動規範に基づいているとはいえない。われわれは、その二つを混ぜ合わせた方法を取り上げたいと考えています。二つのアプローチは同時にやる必要があるのではないかと思うのです」
「都市工学などで、災害時に公共の空間で人間がどういうふうに動き、流れていくのかをシミュレーションすることがあります。あらかじめ予測することによって、建築物や公共空間の設計の時点で災害時の人の動きがスムーズになるようにモニュメントなどの位置を決めることができます。しかし、都市工学の分野は人間を非常にマクロな視点で扱います。要するに人間を点と見なして、その点がどう動くかというものです。なので、実際に身体的な歩きやすさといったところは、無視している。一方、CGアニメーションは非常にミクロな視点で、歩き方がどうなるかということを見ていますが、マクロな視点は欠けています。たとえば、映画で登場するCGの群集は自然には見えますが、それが人間の本当の感覚や行動規範に基づいているとはいえない。われわれは、その二つを混ぜ合わせた方法を取り上げたいと考えています。二つのアプローチは同時にやる必要があるのではないかと思うのです」ちなみに、この研究についてはすでに、10月17日から19日まで開催された、コンピューター・アニメーション・ソシアル・エージェント(International Conference on Computer Animation and Social Agents October 17 - 19, 2005 The Hong Kong Polytechnic University)で発表されている。
 既存のモーションキャプチャの手法に、「地球統計学」という別の領域から応用技術を取り込み、計算の精度を高めるとともに効率化を実現した栗山氏。さらに、そこから生産工学、アニメーション制作、都市工学という別の分野への利用手法を開拓するという展開には、研究の成果を活用して、広く社会への貢献を実現しようとする栗山氏の積極的な姿勢が窺われる。こうした栗山氏の研究姿勢は、画像処理の分野にも新たな展開をもたらしている。
既存のモーションキャプチャの手法に、「地球統計学」という別の領域から応用技術を取り込み、計算の精度を高めるとともに効率化を実現した栗山氏。さらに、そこから生産工学、アニメーション制作、都市工学という別の分野への利用手法を開拓するという展開には、研究の成果を活用して、広く社会への貢献を実現しようとする栗山氏の積極的な姿勢が窺われる。こうした栗山氏の研究姿勢は、画像処理の分野にも新たな展開をもたらしている。「私はこれまで、形状処理や動作データなど、いわば画像生成のための『素材』に関する研究に取り組んできましたが、CG関連の学会で活動してきた影響でしょうか、最近は画像そのものを対象とする研究を始めてみたいと思うようになりました。
画像処理の研究は、すでに長年の蓄積があり、多くの優れた研究者が研究成果を発表しています。そうした中で、自分なりの視点を持って研究したいと思い、CGの技術と画像処理とを統合し、今の時代にあった研究テーマを考えました。今進めているのは、携帯電話のカメラで撮影できる広告などの(2次元バーコードではない)画像にあらかじめ情報を埋め込むためにCGを応用する技術です。たとえば、プレゼントの包装紙の綺麗な絵柄を携帯電話で撮影して、パスワードを入れたらメッセージが出てくるというような仕掛けなどもできるのではないかと考えています。これから、画像情報はどんどん世の中にあふれてきます。そうしたパブリックな空間に、パーソナルな情報空間をつくっていくような手法を研究しています。一端、物理的なものを介して、画像をやりとりするといった手順も増えてくれば、読み込むときの技術として画像処理や特徴量解析を用い、情報を埋め込んだ絵を作るときの技術として、CGが必要になってくる。それがきれいに統合されたものになるような、新しい分野を築きたいなと思っています。まだ始めたばかりなので、このようなアプローチが本当に使いものになるとは断定できませんが、今後の研究成果に期待してください。」
|
||||||||||||