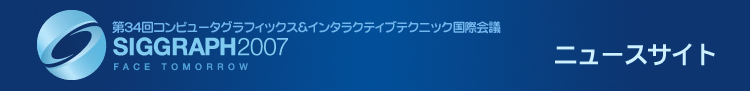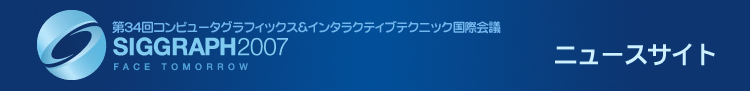現在、デジタル・ドメイン(DD)には、10名弱の日本人アーティストが所属し、同社の手掛ける話題作に大きく関わっている。今回、映像新聞取材班は、SIGGRAPH開催の直前にロサンゼルスのDDにお邪魔し、三橋忠央氏、松原正一氏、東田あすか氏の3人からお話を伺った。
|
|
|
[テクニカル・ディレクター三橋忠央氏]
|
|
●TDは技術者とアーティストの橋渡し役
|

|
三橋氏は、マネックス社、ESCエンターテインメント社などを経て、2006年10月からDDに所属。現在は、テクニカル・ディレクター(TD)として、レンダリングやライティング、シェーディングなどを担当している。代表作は、「マトリックス・リローデッド」「マトリックス・レボリューションズ」「キャットウーマン」「コンスタンティン」など。「M:I-2」も手掛けている。ハリウッド映画に参加する以前は、日本の大学で物理学を学び、卒業後、サンフランシスコの美術大学Academy of Artに留学、そこでCG制作を本格的に開始した。
三橋氏は、TDとしての業務を、「R&Dやプログラマーなどの技術者と、良い目を持ったアーティストを橋渡しすることだ」と説明。制作上最も困難なのが、「締め切りとの闘い」だとしている。
現在は、08年公開のデビッド・フィンチャー監督「The Curious Case of Benjamin Button」(原題)の作業が進んでいる。同作では、主演のブラッド・ピットの80歳の容貌をフルCGで制作するという困難な作業を控える。具体的な制作方法は明かしてもらえなかったが、モデルとする80歳のピットがいないため、モーションキャプチャーは使わないようだ。
|
|
|
●Maya 柔軟なシェーダーへの対応に満足
|
三橋氏の担当は、「メンタル・レイ」を使ったシェーディング。数年前から始まったオートデスク社の「Maya」とのインテグレーションは、基本的な部分が統合されて使い勝手があがってきているという。Mayaはカスタマイズしたシェーダーへの対応も自由で、「柔軟に対応できて助かっている。他の部門とのやりとりなど改善の余地があるかも知れないが、自分が関わるレンダリングの点においてとても満足している」と話している。
三橋氏は今後について「アーティストの部分とテクニカルとしての部分のどちらを伸ばすか迷ったこともあるが、今は両方を伸ばすしかないと思っている。大変な分達成感も強い」と説明している。
|
|
[ライティング・アーティスト 松原正一氏]
|
|
●規模の違いが作品にも反映されるハリウッド
|

|
松原正一氏はライティング・アーティスト。「父親達の星条旗」「硫黄島からの手紙」「トランスフォーマー」などを担当した。TDとしての仕事も多く、日本では年末に公開される映画「ルイスの未来泥棒」(原題「Meet The Robinsons」)では2Dから3D化におけるレンダーマンのパイプラインを開発した。自身ではむしろTD業務の方が好きだという。DD以前は、日本のCM・アニメーション制作会社である白組で働き、ハワイのスクエアUSA(当時)に出向したことがきっかけで渡米した。
日本とアメリカの違いについては、松原氏は、「何よりマシンの台数が圧倒的に違う。その違いが作業のやりたかやでき上がりにも反映されている」と話す。「クリエーターとしては、常によりフォトリアリスティックなものを求められる。分業化されていることで、スキルをより深く掘り下げられる点がアメリカのプロダクションの特徴」だという。
|
|
|
●Mayaの安定したポジションを評価
|
TDとしての業務では、作ったものを自ら勧めていくより、各プロジェクトで求められるツールを作っていくという。作業時は、スクリプトをエディターで書くことがほとんどで、Maya8・5がパイソンに対応したことで作業が楽になったというあ。DD社内では、スクリプト言語にパイソンが標準となろうとしており、「パイソンのライブラリーをインポートして使えることが利点」だという。Mayaには今後、アニメーションのエクスプレッションのパイソンの対応、ハイパーシェードの更なる使いやすさを求めたいとしている。
TDとしての松原氏は、Mayaは3Dアプリケーションとして何かに特化しておらず、どのようなデータも読めることが良いと考えているという。DD社内では、Mayaから直接レンダリングすることがないため、「メーカーとして目玉機能をアピールするというより、むしろMayaは安定して周辺とデータをやりとりできるベースのような存在であってほしい」と話している。
|
|
[ライティング・テクニカル・ディレクター 東田あすかさん]
|
|
●分散レンダリングのサポート
|

|
DDで4年目を迎える東田あすか氏は、ライティング・テクニカル・ディレクター。ライティングのアーティストの技術サポートやツール開発、パイプラインのコンサルテーションを担当。最近では、「アイロボット」、「父親達の星条旗」「硫黄島からの手紙」、「パイレーツ・オブ・カリビアン3」などに参加した。プログラムのバックグラウンドを生かし、分散レンダリングのサポートをすることが多い。現在興味を持っているレンダラーはメンタル・レイ。「これまでレンダーマンを使用していたが、少し目先を変えてみたいのと同時に、新しいものに取り組むことで現状が最適化されているのか知りたい」のだという。
東田氏はDD以前、日本のCGプロダクション、トリロジーで勤務。そこで感じた問題点を解決すべく、慶応大学SFCの研究所で研究員として学んだ後渡米した。東田氏は「日本では作品に対するチームの規模が小さい。(個人に負担がかかることが多いため)情熱をぶつけるにはそれでも良いが、ビジネスとしては行き詰まるのではないかと思った。どんな手段を使ったら日本の現場を助けられるのかと考えたとき、日本には技術的な素養を持った少ないことに気づき、そういったスタッフの中で仕事がしたいと思った」と話す。
実際にDDに来て、最も感じるのは文化の違いだという。「日本は、その日のうちに出来ることをする。DDではその日計画どおりに終わればよいとする。さらにスケジュールを管理するコーディネーターによる管理、チェックが入ることで、やりやすいこともその逆もあると感じている」と話す。
|
|
|
●Mayaの直感的なインタフェースを評価
|
今後はチーム全体をより見渡せる立場に就きたいと語るとともに、「NUKE上でシェーダーのパラメーターを再構築し、シェーダーそれぞれがデフューズやスペキュラー、リフレクションの値などを別々のイメージにわけ、合成の際に調節ができるようなシステムの構築を進め、それを現場に反映させたい。またシーンの中にライトを置き、それぞれをレンダリングし、合成の際に構成し直すというプロジェクトを実現したい」という。
Mayaはレンダーマンとの組み合わせで使用される。直感的なインターフェースはアーティストにとって最適であり、パイソンとの統合で、GUIを作るのが便利になり、インタープリターでマルチスレッドのプログラムを走らせられるようになった」と話している。
|
|
▲ページトップに戻る
|
|
|